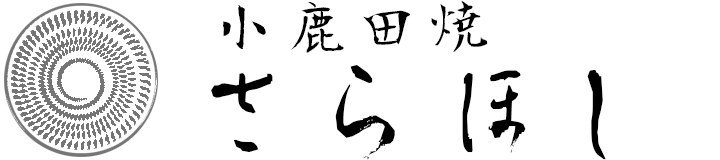2022/11/30 06:17
リンク: 小鹿田焼の特徴と技法 小鹿田焼の里
「小鹿田~おんた」地名の由来

小鹿田焼の里は、大分県日田市中心部より北に約16kmの山間部に位置します。「小鹿田」は「おんた」と発音します。もとは「鬼田」と表記したようです。全国的にもある「おんた」は「隠田」とも書き、隠し田(年貢の徴収を免れるため密かに工作された水田)を意味します。深い山奥にあるため隠し田があったとも考えられます。小鹿田は土地が狭く荒地が多いことから「鬼」の字を用いたのか、「鬼カ田」「鬼ガ田」とも表記し、鹿の生息地でもあったことから「鬼鹿田」へ、さらに「小鹿田」へと転化していったのではないかと伝えられています。
小鹿田焼の歴史

小鹿田焼の開窯は江戸中期1705(宝栄2)年とする古文書があり約300年の歴史があります(※1)。全国有数の杉の産地で江戸幕府の天領地であった水郷・日田の生活雑器を賄うために官令によって興されたました。日田の代官が筑前の国(福岡県) 小石原焼の陶工・柳瀬三右衛門を小鹿田に招いて技術を伝授され、資本金は黒木家、土地は坂本家が提供し開窯されました。この柳瀬、黒木、坂本の三家体制で始まった小鹿田焼の窯元は10軒ほどで、共同で地元の土を採取し、朝鮮系の登り窯を用いて生活雑器を作り、日田領内に賄っていました。作品は実用品ばかりで、壺、鉢、茶碗などの多様に渡り、全てを自給せねばならない山間僻地の地理がそうさせようです。全て手作業で行われる作陶は、集落の農閑期に行われる半農半陶の生活の中で、親から子へと一子相伝の家業として継承されてきましたが、山奥の寒村の農家の副業にすぎず、広く世に知られることはありませんでした。小鹿田焼の大半は、リヤカーや牛車に積まれ、何時間もかけて日田まで運び、日田の問屋を通じて豊前、豊後(大分県)地方一円に売られ、「日田もの」「日田焼」と呼ばれていました。
(※1)近年の研究では享保年間(1716-1735年)とする見解がある。

大正後期から昭和初期にかけて小鹿田焼は転換期を迎えます。「小鹿田焼」の呼称が使われ、以後定着するようになり、この頃、現在の小鹿田焼を代表する技法「飛び鉋」「打ち刷毛目」が取り入れられました。小鹿田焼の最初の紹介者は、民藝運動(※2)の指導者であり思想家の柳宗悦(むねよし)氏です。柳氏が「日本のものとして誇ってよいもの、即ち正しくて美しいもの」を探す民芸品蒐集の旅の中、福岡県久留米市の陶器店で小鹿田と出会い、その不思議な品々に心を惹かれます。しかし、調査の甲斐なく窯の正確な場所が分からず、柳氏が小鹿田を訪れるのは4年後の昭和6年になります。柳氏は、この不思議なやきものの素性を確かめるため、単身で山道を歩き、峠を越え、土地の人が皿山(※3)と呼ぶ場所を訪れます。小鹿田焼が昔の手法がそまま残されていることを大変貴重とし、小鹿田焼の伝統技法と質朴な作調を称賛し、無心に暮らしの品々を生み出している人達の姿勢を崩すことのないように助言しました。そして、雑誌「工芸」に掲載された紀行文「日田の皿山」(※4)で小鹿田焼を紹介しました。第二次大戦後の昭和25年には、陶芸の第一人者である浜田庄司氏(人間国宝)が小鹿田を訪れ、小鹿田焼の技術保存について懇談。また、昭和29年には、世界的にも著名な英国の陶芸家であるバーナード・リーチ氏、浜田庄司氏、河井寛次郎氏(陶芸家)が小鹿田焼に訪れました。リーチ氏は三週間逗留して作陶を行ない、当時の様子を著作「日本絵日記」に残し、国内から海外にまで広く紹介しました。小鹿田焼は民藝運動に携わる人達によって世に紹介され、日本の代表的な民陶として高く評価されるようになりました。
(※2)民藝・・・「民衆的工藝品」の略。思想家の柳宗悦氏によって、日本各地で作られる職人の手仕事で作られる日用品に与えられた言葉。柳氏は、名も無き職人が庶民の為に作った日用品のなかに、芸術家が作った鑑賞用の美術品とは異なる、機能的で健康的な美しさを見出しました。柳氏はこれを「用の美」と表現し、その素晴らしさを広く世に伝える運動を行いました。
(※3)皿山・・・皿を造る所、焼き物のできる場所の意味。
(※4)工芸の愛読書であった秩父宮様(昭和天皇の弟君)が小鹿田焼に興味を持たれ、お買い上げの上、村に金一封を送られたというエピソードが残っている。

昭和30年〜40年代には民陶ブームと共に小鹿田焼の需要は急増しましたが、窯元たちは、機械化せずに手作りの伝統を守り続ける道を選び、1975年には、全ての窯元が専業化しました。小鹿田焼は開窯以来、外部からの弟子を一切取らず「柳瀬家」「黒木家」「坂本家」の子孫だけ(小袋窯は黒木家の系統)に受け継がれたため伝統的技法がよく保存されており、国は1970年に小鹿田焼の技術を「記録作成等の措置を構ずべき無形文化財」に選択。さらに、1995年に国の「重要無形文化財」に指定、釜元によって構成される団体を国の重要無形文化財保持団体に指定しています。小鹿田焼は、今も、柳氏の「猥に昔を崩さぬ様」という教えに沿って、9軒の窯元が永い歴史と伝統を守りながら日常の暮らしの器作りの手仕事に取り組んでいます。

参考:「小鹿田焼陶芸館」「小鹿田焼公式パンフレット」「小鹿田焼(芸艸堂)」「日田の皿山(柳宗悦)」