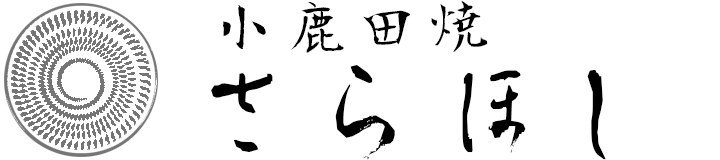2022/11/30 06:14
小鹿田焼とは

小鹿田焼は、大分県日田市の山あいの小さな集落で、江戸中期より受け継がれた昔ながらの伝統技法で作られる民藝の陶器です。谷川の水力で土を砕き、足で回す蹴轆轤、薪を使う登り釜で焼くという、小鹿田焼の全ての工程が自然の力と人の手仕事でできています。飛びかんな、打刷毛目、指描き等の独特の模様があり、職人の手業によって作られる素朴な風合いは、温かみと美しさ、奥深さがあり、伝統が持つ力強さがあります。窯を開いた当初から約300年の歴史を持つ伝統的で地域的な陶芸技法がそのまま保存されており、国は1970(昭和45)年に小鹿田焼の技術を「記録作成等の措置を構ずべき無形文化財」に選択。さらに、1995(平成7)年に国の「重要無形文化財」に指定、釜元によって構成される団体を国の重要無形文化財保持団体に指定しています。
小鹿田焼の特徴
小鹿田焼は、工業製品が主流の現代に至るまで、約300年間、伝統の技だけで活きのびてきました。その技術の保存、継承、向上のため、職人は他所には無い拘りと知恵と工夫で手仕事に取り組んでいます。
機械を使わない
小鹿田焼は、機械を使わずに、川の流れを動力にした唐臼(からうす)、足で回す蹴轆轤(けろくろ)、薪を使った登り窯で焼かれます。全ての工程が自然の力と人の手仕事で作られます。
手作りの道具
成形用のヘラ、コテ、叩き板、装飾用の鉋、櫛など工程に必要な道具は、各職人によって自分の手に馴染むように作られます。
絵を描かない
刷毛目、飛び鉋、指描き、櫛描きなどの独特な文様、釉薬の掛け模様など、手業ならではの素朴な味わいが特徴です。
登り窯で焼く
小鹿田焼は、現在も昔ながらの薪を燃やす登り窯で焼かれます。一般に均一に焼け安定感のあるるガス釜、電気釜が主流の中で、登り窯は焼成が難しく、2~3割は割れなどで売り物になりません。薪の灰が自然釉になって焼き物ならではの風合いになる。人の手で操った炎で焼かれた焼き物は自然だけが持つ揺らぎの味わいがある。焼き加減によって出来上がりが変わる。日本全国でも少なくなっており、あっても作家、美術家が使用することが多く、小鹿田焼のように職人が日用品を作る窯は稀です。
窯元の名を入れない
作品には個別の窯元名は入れず「小鹿田焼」の印を押します。原土の採集から作品づくりまで外部の手を入れず窯元で作陶を行い、小鹿田焼同業組合によって管理される地域ブランドです。
一子相伝
陶芸技法は一子相伝で親から長男に伝承され、作陶は全て家族ぐりみで行われます。外部から弟子を取ることはしなかったため、伝統が守られてきました。
小鹿田焼の技法

飛び鉋 (とびかんな)
古時計のゼンマイなどの弾力性のある金属で作った鉋でを押し当てて、リズミカルにバウンドさせながら土を削り出し、連続した細かい文様をつける技法です。
刷毛目 (はけめ)
化粧土を掛けた後、刷毛を連続的にあてて濃淡をつける技法です。刷毛をあてた部分の化粧土が剥がれ、下地の部分が焼くと黒くなります。

櫛描き
木材で半月の櫛状の道具を作り、ゆるやかな波型の曲線を描き出す技法です。
指描き
化粧土が乾かないうちに、指でジグザグの曲線の連続文様を描く技法です。

打ち掛け
釉薬を柄杓にくみ、水をまくような動作で作品に勢いよく打ち掛ける技法です。飛び鉋や打ち刷毛目と併用することが多く、即興的な面白さがあります。
流し掛け
スポイトや柄杓により作品全体に流れるように掛ける技法です。
小鹿田焼ができるまで
自然と人の手によって作られる小鹿田焼は、工程ひとつひとつに独自の工夫がなされています。

原土の採取
陶土の原料となる原土は、集落近郊の採土場で1年に一度、9軒の窯元が共同で採取して等しく分配します。小鹿田焼では全てが平等です。原土は腰が強く粘りがあるが伸ばしにくい難点があります。また、鉄分を多く含み赤みがある土は、焼成後、黒みを帯びます。採取した土を10日程乾燥させ、木槌でこぶし大くらいの大きさにします。
唐臼による原土の粉砕
昔ながらの水力を利用した装置・唐臼(からうす)で乾燥を終えた原土を粉砕します。20日から30日をかけて粒子状にします。

水簸(みずひ)
粒子状にした原土を水槽に入れ、舟の櫂に似た道具で漕ぐように交ぜ、できた泥水はふるいで何回も濾してごみや砂を取り除きます。濃縮した泥土を「オロ」と呼ばれる濾過槽で水抜きし粘土質を取り出します。さらに、天日や窯の上で乾燥させるときめが細かく粘りのある小鹿田焼の陶土になります。陶土にするまで半月~20日ぐらいかかります。土作りは轆轤(ろくろ)に座らない家族、主に年寄りや女性が担います。寒い冬には辛い作業で、昔は「皿山(皿のできる場所)は女の地獄。嫁にやるな」といわれていたそうです。

成形
出来上がった陶土は、成形前に手で菊練りをしてよく練りまれ、含まれた空気を抜いて硬さや成分を均一にします。成形は人力の足で蹴って回す蹴轆轤(けろくろ)を使って行います。轆轤(ろくろ)は1軒に2台、当主と長男に与えられます。窯で焼くと2割ぐらい縮むため大き目に成形します。作品の大きさ等により「引きづくり」、「玉づくり」、「紐づくり」の3つの手法を使います。電動ではなく、足で蹴って轆轤を操るため完全に均一とはいかず、それ故素朴な味わいと面白味が出ます。小鹿田焼の陶土はきめが細かく腰が強いため伸ばしにくく、耐火性にやや劣り収縮率が大きいため割れやすいという難点があります。一般に多くの窯場では数種類の土を混ぜて使いますが、小鹿田焼では産地の特色が薄れるため混ぜることはしません。成形で割れにくい工夫をして欠点を補います。底部を小さくした重心が上にある独特のバランスは土の特性からくる小鹿田焼ならではの特徴です。
乾燥
成形が終わった器は板に乗せ、「ツボ」と呼ばれる家の前庭で天日干しします。1時間に1回程度器の向きを変えて太陽光と風が全体にあたるようにします。

鉋、化粧土による装飾
小鹿田の土は鉄分が多くそのまま焼くと黒色になります。白い化粧土などを掛けて模様を施します。伝統的な装飾として「飛び鉋」、「刷毛目」、「指描き」、「櫛描き」などがあります。蹴轆轤を回転させながら装飾を施します。最後に小鹿田焼の証である印が押されます。
施釉
釉薬による伝統的な装飾として、作品に柄杓で打つように「打ち掛け」と、作品全体に流れるようにかける「流し掛け」が代表的な技法です。釉薬の原料は木灰、藁灰、長石、鉄、銅などで天然のものだけを使用します。
素焼き
小物や濃い釉薬の作品には素焼きを行います。割れや釉薬が飛んでしまうのを防ぐためです。
登り窯による焼成
江戸時代から伝わる登り窯で薪を焚いて焼成を行います。登り窯は袋と呼ばれる焼成室が斜面に階段状に連なっており、下から順番に薪を焚いていきます。焼成室の間には火の通り道があり、火の熱が下から上へ登っていくようにできており、陶器を大量に作るのに適しています。薪は主に杉の製材所の割き落としや家屋の廃材を使います。火を入れると、約30時間つきっきり寝ずの番で夜通し焚き続けます。窯焚きの温度は約1250度。温度計での計測はせず、窯の状態を見て経験で薪を追加します。窯の中の場所でも火のあたりや温度が異なり、焼き上がりの色や質感が変わります。窯入れのときは、器の種類や火の流れを考えて慎重に置き場所を決めます。窯の中の温度が高温に達すると釉薬が溶けて器を覆い、強度と防水性を高めるとともに色を変化させます。薪の灰が器にかかり自然釉となって思いもよらぬ変化をもたらすこともあります。自然の炎のゆらぎが登り窯ならではの風合いを器に与えてくれるのです。最後の薪が燃え尽きる寸前に焚き口をレンガと泥で塗り固めます。火の管理は熟練の職人でも難しく、判断を誤れば、ひび割れなどで多いときは半分がダメになるそうです。
完成
2~3日冷やして窯から出される器は、登り窯による焼成や手作業によって偶然生まれてくる色の違いや色むら、たわみなどの手作りならではの独特な味わいがあります。同じものはひとつとなく、全てが世界にひとつだけの品として生まれ、使用者と出会います。その素朴な風合いは、なぜか和洋を問わず色々な料理を引き立ててくれ、料理を選びません。小鹿田焼は、工芸的美術品ではなく、あくまで日用品として暮らしに必要とされる「用」に叶う物作りから生まれる実用の生活雑器なのです。それぞれの家庭の日常の暮らしの中で使われて完成される、そんな存在感のある器です。
参考:「小鹿田焼陶芸館」「小鹿田焼公式パンフレット」
ショップはこちら
※ 当サイトの情報を転載、複製、改変等は禁止いたします ※